 |
 |
| No25365−37 | No25365−38 | ||
| 冨田山城 | 観音堂城 | ||
| (とみたやまじょう) | (かんのんどうじょう) | ||
 |
 |
| 冨田山城 北面の土塁 | 観音堂城 虎口 |
| ◆ 城郭の概要 | ◆ 城郭の概要 | |
| 別 名 : 北上野城 | 別 名 : 勘四郎山城 | |
| 所在地 : 甲賀町上野字東谷 | 所在地 : 甲賀町上野字東谷 | |
| 築城年 : 室町時代 | 築城年 : 室町時代 | |
| 形 式 : 丘城 | 形 式 : 丘城 | |
| 遺 構 : 土塁、虎口、虎口受け | 遺 構 : 土塁、堀切、竪堀、虎口、虎口受け | |
| 訪城日 : 平成25年3月16日 | 訪城日 : 平成25年3月16日 |
| ◆ 歴 史 |
|
・・・・冨田山城・・・・は、当城の南方の平地に冨田屋敷の伝承地があり、上野冨田氏の山城と云われるが、城歴等の詳細は不明である。 |
| ◆ 構造と感想 |
| ・・・・冨田山城・・・・は、甲賀町上野のうち北上野集落の北側に、東から西にのびる丘陵から南の平地部に向かって突き出した尾根の先端部が二股に分かれた西側の尾根に築かれている。東側の尾根には観音堂城が築かれており、両城の間は100m程である。 冨田山城の構造は、頂部に方形の主郭を置き、南側に帯郭状の虎口受けを伴った、基本的には甲賀に一般的な単郭方形タイプの城である。 主郭は四方を土塁で囲んでいるが、地形の制約を受け、南北に長く、中央部がくびれるいびつな長方形をしている。土塁は、南北面が自然の瘤状の高まりを活用し大規模であるが、東西面は盛土により築造されたもので低く小さなものである。東面の土塁は、人一人がやっと通れる幅しかなく、中央付近のクランク状の折れも、自然地形の制約を受けた結果と見られている。西面の土塁は、東面よりやや巾が広く、天端での人の活動が想定できる。 開口は、南東隅と南西隅の二ヶ所にあるが、南西隅の開口は細く、二段築成の郭内の西側下段に繋がっており排水溝と見られている。南東隅の開口が虎口で、南に出ると東西に細長い虎口受け、そこから南側の平地部に降り下りたと思われるが、城道は残存せず、現在は東側の裾にある養徳寺観音から斜面を登り東面土塁に至る道が付けられている。 ・・・・観音堂城・・・・は、北西端の堀切で背後の丘陵続きを遮断し、その南東側の尾根頂部に北、東、西をコの字形の削り残しの土塁で囲んだ主郭を置き、南東隅に坂虎口が開き、虎口を出ると塹壕状の虎口受け、それから東側に回り込むと腰郭が続く構造をしている。 主郭の土塁は、北面が分厚く高さも高く、特に北西隅では壇状に高まり、物見台や烽火台と考えられている。また、西と東面の土塁は、南に向かって高さと巾を減じており、自然地形を反映したものと思われる。南側は切岸で防禦している。 虎口の両側は、郭からの土塁状の張出しでそそり立ち、幅も一人がやっと通れる広さである。西側は竪土塁としてのび、虎口受けの土塁西端部が喰い違い虎口状に突出している。 この城は、土塁囲みの単郭方形を踏襲しつつ、虎口などに高度な防御技術を駆使した城である。 |
| ◆ 道 案 内 | ||
| ・・・・冨田山城・・・・は、新名神高速道を甲南インターで下りた最初の交差点である甲南IC口交差点で左折し、広域農道に入り560m程北進すると新治口交差点に至る。新治口交差点で右折して、東に2.4km程行くと突き当たりのT字路に至る。T字路を左折し360m程北東に行くと県道4号線の野尻交差点に出る。そこを右折し県道4号線に入り、南東に道なりに5.1km程行った田堵野西交差点を直進する。県道51号線に入り南東に320m程先の油日農協前交差点で左折し、市道に入る。北東方向に550m程行った丘陵登り手前の十字路で右折し、東に入る。農道を道なりに420m程進むと左手に養徳寺観音への参道(矢竹に覆われ刈り払いされていないと見つけ難いので注意。)がある。北に5、60m入ると小さな観音堂があり、その背後上方が城跡である。 ・・・・観音堂城・・・・は、養徳寺観音への参道から60m程東進するとT字路があり、T字路から東に50m程行った左手が城跡である。 |
| ◆ | TOPへ | 戻る |
 |
 |
|
| 冨田山城 虎口受け | 観音堂城 北端の堀切 | |
 |
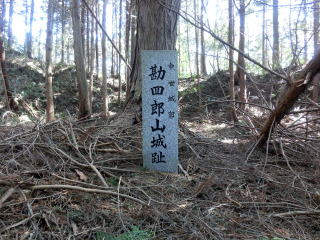 |
|
| 冨田山城 城址碑 | 観音堂城 城址碑 | |